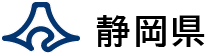茶業研究センターに寄せられた技術的な問合せへの対応
| お問合せ内容 | 回答 |
|---|---|
| 被覆栽培の基本的な技術について教えてほしい | ・一般的に行われている「直がけ」被覆について紹介します。 ・かぶせ茶の場合は約2葉期から2週間程度、てん茶の場合は約2葉期から3週間程度被覆します。 ・被覆資材は遮光率が75~85%の資材が主に使用されています。 |
| 高温に強い品種について教えて欲しい | ・国が2014年に示した資料では、「さえみどり、あさつゆ、ゆたかみどり、静印雑131、くりたわせ、そうふう」が高温に強いとされています。 ・静岡県が育成した多収性品種の「つゆひかり、しずゆたか」などは、近年の気象条件下でも生育が極めて良好なため、高温に強いと考えています。 |
| かん水のタイミングを教えて欲しい | ・夏季の高温少雨時や冬季の干ばつ時は、かん水を行うことで茶樹の生育を健全に保つことができます。 ・茶園の1日当たりの水消費量は、夏季は約5mm/平方メートル、冬季は約1mm/平方メートルです。 ・土壌pF値(土壌中の水が土の毛管力で引き付けられる強さを示す値であり、数値が低いほど土壌が湿っており、植物の根が水を吸いやすいことを示す)が2.3がかん水の目安と言われています。 ・スプリンクラーがある場合は、夏季は1回25~30mm/平方メートルを7日程度毎にかん水するのが望ましいです。 ・夏季にかん水することで秋季の生育量が1.6倍に増加したという結果もあります。 |
| 中切り後の再生芽が出てこない | ・これまでで一番深い位置で中切りした場合は、再生芽の生育が遅れますが、2ヶ月ほどすれば必ず再生芽が出てきます。 ・幹が古い場合は、潜伏芽が表皮の深部に埋没しているため、再生芽の生育が遅れます。 ・前回の中切り位置よりも少し上でせん枝した場合は、幹が若く、潜伏芽が表皮の浅い部分に潜伏しているため、再生芽の生育が早くなります。 ・中切りする場合は、毎回同じ高さでせん枝するのではなく、計画的に高さを変えて行うことも必要です。 |
| 台切りした場合は、何年で茶園が回復するか教えて欲しい | ・6月に地上15cmで台切りした結果、1ヶ月後には芽が出始め、2ヶ月後には新芽が旺盛に生育します。 ・翌年の3月まで伸ばしてせん枝を行い、二番茶期と秋季にせん枝して、2年後の一番茶から摘採できるようになります。 |
| 秋整枝の時期について教えて欲しい | ・秋整枝の目安は、日平均気温が18~19℃以下になった時期です。 ・これよりも早く秋整枝を行うと再萌芽し、冬の間に芽が壊死してしまいますので留意してください。 |
| お問合せ内容 | 回答 |
|---|---|
| てん茶適正が高い品種を教えてほしい | ・静岡県の奨励品種の中では、「つゆひかり、香駿、おくみどり」が外観やから色が優れ、香気、滋味は「さえみどり」が優れる傾向です。 ・また、収量的には、「さやまかおり、さわみずか、香駿、つゆひかり、おくみどり」が多い傾向です。 ・「つゆひかり」は生育が良く、炭疽病にも強いため、有機栽培によるてん茶適性も高いと考えています。(「しずゆたか」のてん茶適性については、現在調査中です。) ・一方、近年、農研機構で育成した「せいめい」などもてん茶適性が高い品種です。農研機構HPで特性が公開されておりますので、参考にしてください。 |
| 「つゆひかり」「しずゆたか」の苗木を入手したいがどうしたらよいか | ・「つゆひかり」「しずゆたか」は静岡県と許諾契約を締結した静岡県経済連や島田品種茶普及会などが販売しております。 ・許諾契約先は県のHPで公開しておりますので参考にしてください。 ・両品種とも需要が多く、定植間際の注文では苗木の入手が困難です。購入の際は早めに予約注文することを推奨します。 |
| お問合せ内容 | 回答 |
|---|---|
| クワシロカイガラムシの防除時期について知りたい | ・クワシロカイガラムシの防除時期は本種の孵化最盛期から3~5日後となります。 ・各地区における本種の防除時期については静岡県病害虫防除所が情報を公開しておりますので参考にしてください。 |
| ハマキガ類やヨモギエダシャクの防除時期について知りたい | ・ハマキガ類及びヨモギエダシャクの防除時期は成虫の最盛日から7~10日後となります。 ・茶園での蛾の発生が見られましたら、静岡県病害虫防除所が公開している害虫誘殺グラフを参考に防除時期を決定してください。 |
| 炭疽病の防除対策について知りたい | ・炭疽病は、萌芽期から出開きをするまでの間に感染し、特に1.5葉~2葉期頃が感染しやすいです。 ・この期間に発病から茶葉を保護するため、萌芽~1葉期に予防剤を、2~3葉期に治療剤を散布すると高い防除効果が期待できます。 ・DMI剤は、高い効果が期待できますが、耐性菌の発生を避けるため、連用しないようにしてください。 |
| お問合せ内容 | 回答 |
|---|---|
| 有機栽培における施肥設計を簡便に実施したい。 | ・有機質肥料の施肥設計試算シートを用いると、より簡便に施肥設計が可能です。 ※各有機質肥料の一般的な値から算出する参考値を表示している旨、ご了承願います。 |
| チャの亜鉛欠乏症への対策について知りたい | ・チャの亜鉛欠乏症は二番茶以降に発生しますが、炭疽病、もち病等の防除に用いられているZボルドー水和剤を散布することで発生を防止できます。 ・Zボルドー水和剤は400倍液とし、萌芽期に1回以上散布してください。 |
| 石灰窒素を施用すると、茶葉が硬くなるのか? | ・石灰窒素単体を施用した試験結果はありませんが、苦土肥料と同時に施用することで、慣行施肥と同等の収量が維持されます。 ・品質に関与する全窒素含有率も慣行施肥と同等で、「茶の硬さ」に関与すると考えられるカルシウム及び中性デタージェント繊維の含有率も慣行施肥と同等である結果が得られています(参考資料1)。 ・このため、苦土肥料と同時に施用し、その施用量が窒素量換算で12kgN/10a程度までであれば、石灰窒素の施用によって茶の収量や品質が低下する可能性は低いと考えられます。 ・石灰窒素の施用により「茶が硬くなる」と感じられる要因には、土壌の塩基バランスとしてカルシウムが過剰になってしまうことや、施用量の多さから土壌pHが適正な範囲を超えてしまうことが可能性として考えられます。 ・過去の研究報告において、カルシウム肥料単体の過剰施用により、茶の収量が低下することが報告されています(参考資料2)。 ・上記の資料においても、苦土肥料と同時施用した場合であっても、石灰窒素の施用量が多いと土壌pHが適正範囲を超える場合があることから、施用前に土壌分析により土壌pHや土壌の塩基バランスを確認のうえ、適切な施用量を御検討ください。 |
| 尿素の葉面散布の適切な濃度は? | ・日差しの強くない朝夕に散布することが望ましく、1~3葉期の新芽に対しては0.5~0.8%、成葉に対しては1%程度が適切とされています。 ・日差しの強い日中に散布すると、上記の濃度であっても濃度障害が発生する場合があるため注意願います。 (参考資料:茶大百科2巻の400ページを参照)。 |
| 牛ふん堆肥の施用量の目安は? | ・過去の研究結果から、2t/10aの施用量では茶葉の収量及び全窒素含有率が慣行区と同等程度となりました。 ・6.6t/10aの施用量では土壌pHが施肥基準以上に高まり、収量が低下した研究事例があります。このため、施用量は2t/10aまでを上限に、施用前の土壌診断結果に基づき決めることを推奨します。 ・牛ふん堆肥にはリン酸、カリウム、カルシウムが多く含まれているため、牛ふん堆肥に含まれるこれらの肥料成分の施用量を考慮し、その分通常のリン酸、カリウム、カルシウムの施用量を調整して、土壌中の肥料成分が過剰にならないようご留意ください。 |
| 春肥、夏肥、秋肥いずれかを削る場合、一番茶に最も影響が少ないのはどの時期の施肥か? | ・夏肥が最も影響が少ないと考えられます。 ・春肥を削ると一番茶生育初期から茶葉の全窒素含有率が低下するため、春肥を削るのは望ましくないと考えられます。 ・夏肥、秋肥を削ると、一番茶生育初期の茶葉の全窒素含有率は削らない場合と差はありませんが、生葉収量の増加に伴って削らない場合に比べて低くなります。 ・一番茶の窒素養分の転流源となる成葉の全窒素含有率の推移を調査した結果から、夏肥を削っても、秋肥の施用により成葉の全窒素含有率は削らない場合と同等の数字に戻ります。 ・秋肥を削った場合は一番茶生育期の成葉の全窒素含有率が低くなる調査結果となりました。 |
| 深耕を行う最適なタイミングはいつか? | ・8月中旬から9月上旬頃までが良いとされていますが、夏季に干ばつを受けた茶園では実施すべきではありません。 ・深耕により、圧密化した土壌の物理性を改善できることに加え、古い根を更新して、肥料成分の吸収根の再生を促すことができます。 ・しかし、干ばつを受けている/受けた茶園(または、深耕予定日以降に降雨が期待できない茶園)において深耕を行うと、茶の水分吸収を悪化させ、干ばつの被害を甚大化させてしまいます。 ・また、地温が低いと根の再生が進まないため、冬季から春季に深耕すると一番茶生育期に肥料吸収効率が低下するため、この時期の深耕は望ましくありません。(参考資料:茶大百科2巻の339及び354ページ) ・なお、土壌圧密化対策として深耕を行う場合、堆肥やもみ殻等の有機物施用と併せて実施することにより、長期的な土壌物理性の改善が期待できます。 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林技術研究所茶業研究センター
〒439-0002 菊川市倉沢1706-11
電話番号:0548-27-2311
ファクス番号:0548-27-3935
ES-kenkyu@pref.shizuoka.lg.jp